| 1.開催概要 |
| 日 時:平成29年8月8日(火)〜9日(水) |
| 会 場:東京都千代田区 「日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館」 |
発表件数:114編
聴講者数:約500名 |
| 開催のお知らせ及びプログラム |
| 2.セッション名及び座長・副座長は次のとおりである。 |
| |
1.交通制御・規制・取締り |
座 長:松本 幸正(名城大学)
副座長:兒玉 崇(阪神高速道路(株)) |
| |
2.交通流 |
座 長:中村 英樹(名古屋大学)
副座長:岡田 良之((株)長大) |
| |
3.情報提供・運転支援 |
座 長:内田 敬(大阪市立大学)
副座長:鈴木 弘司(名古屋工業大学) |
| |
4.運転者認知・挙動 |
座 長:田久保 宣晃(科学警察研究所)
副座長:中村 俊之(名古屋大学) |
| |
5.交通安全(1) |
座 長:小林 寛(国土技術政策総合研究所)
副座長:井料 美帆(名古屋大学) |
| |
6.交通安全(2) |
座 長:山中 英生(徳島大学)
副座長:海老澤 綾一(警視庁) |
| |
7.自転車交通 |
座 長:日野 泰雄(大阪市立大学)
副座長:高砂子 浩司((一財)計量計画研究所) |
| |
8.歩行者交通 |
座 長:久保田 尚(埼玉大学)
副座長:山口 敏之(セントラルコンサルタント(株)) |
| |
9.駐車管理 |
座 長:瀬戸下 伸介(国土技術政策総合研究所)
副座長:倉内 慎也(愛媛大学) |
| |
10.都市交通調査とデータの応用 |
座 長:佐々木 邦明(山梨大学)
副座長:シン ジャン((株)高速道路総合技術研究所) |
| |
11.交通容量・サービス水準 |
座 長:大口 敬(東京大学)
副座長:荒川 太郎(首都高速道路(株)) |
| |
12.道路計画・道路構造 |
座 長:外井 哲志(九州大学)
副座長:塩見 康博(立命館大学) |
| |
13.公共交通(1) |
座 長:遠藤 玲(芝浦工業大学)
副座長:山田 大輔(国土交通省都市局) |
| |
14.公共交通(2) |
座 長:原田 昇(東京大学)
副座長:吉田 樹(福島大学) |
| |
15.交通行動分析 |
座 長:奥村 誠(東北大学)
副座長:日下部 貴彦(東京大学) |
| |
16.都市交通計画 |
座 長:高山 純一(金沢大学)
副座長:関本 義秀(東京大学) |
| 3.座長・副座長総括報告 |
| 4.研究奨励賞(3件)及び安全の泉賞(2件) (〇は発表者、論文番号順) |
| |
<研究奨励賞・安全の泉賞> |
| |
論文番号51.「子どもの道路横断判断にまつわる保護者の実態認識に関する実験的研究」(研究論文)
| ○ |
府川 阿佐美 |
日本大学 |
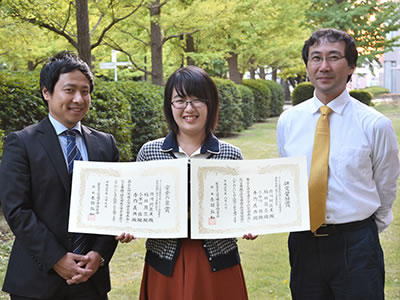 |
| |
稲垣 具志 |
日本大学 |
| |
小早川 悟 |
日本大学 |
| |
寺内 義典 |
国士舘大学 |
| 研究要旨 |
子どもの交通事故は年々減少傾向にあるが,さらなる交通安全対策が必要である.道路横断に大きな課題を抱える子どもの特性を踏まえ,これまで「認知」における交通安全教育が多くなされてきた.しかし「判断」を誤ることにより飛び出しに至るケースも考えられることから,道路横断判断の観点を取り入れた教育も必要である.本稿においては,日常生活における安全教育者として最も身近な存在である「保護者」を対象に,自身の子どもの横断判断能力の認識状況を実験により把握した.その結果,子どもは車両速度を考慮しないで横断判断しているのに対し保護者は車両速度を考慮すると予想しており,子どもの実態と保護者の認識との間に乖離があることにより子どもの横断判断能力を過大評価していることが示された.さらに2年生の親子ではどの速度帯でも実態認識差が大きい一方,5年生の親子では高速になるにつれて実態認識差が大きくなる傾向がみられた. |
|
| |
<研究奨励賞> |
| |
論文番号69.「機械学習とスマートフォンを用いた道路の損傷画像のリアルタイム検出と維持管理基準の作成」(研究論文)
| ○ |
前田 紘弥 |
東京大学 |
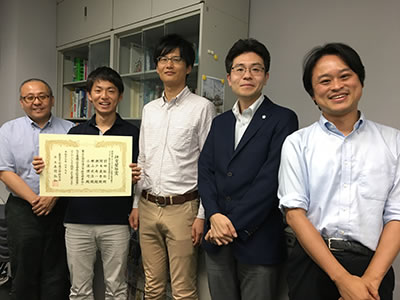 |
| |
関本 義秀 |
東京大学 |
| |
瀬戸 寿一 |
東京大学 |
| |
樫山 武浩 |
東京大学 |
| |
小俣 博司 |
東京大学 |
| 研究要旨 |
課題先進国と言われる日本のインフラ維持管理は,財源・専門家不足が深刻であり問題となっている。一方で,ここ数年の深層学習等の技術発展により高度な画像認識が可能になっており,さらに世界中広く普及しているスマートフォンのカメラ機能は高精細化している。
そこで本研究では,7つの自治体の道路管理者と連携し,深層学習により路面損傷画像のリアルタイム検出を行うとともに,ランダムフォレスト法により自治体ごとの維持管理水準の自動生成を試みた。その結果,一般的なスマートフォンのみを用い,路面損傷を検出率(真陽性率)89%で検出することができ,自治体ごとの維持管理水準の違いを垣間見ることができた。この成果により,安価で簡易なインフラ点検が可能となり,財源・専門家不足に悩む諸地域においてブレークスルーとなる可能性がある。 |
|
| |
<研究奨励賞> |
| |
論文番号78.「片側2車線高速道路における付加追越車線方式の試行運用」(実務論文)
| ○ |
川島 陽子 |
中日本高速道路(株) |
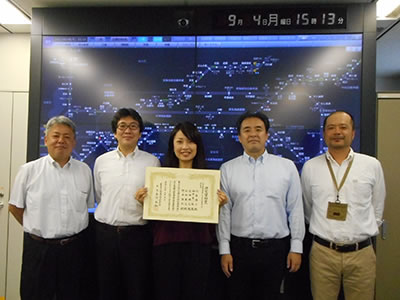 |
| |
田中 真一郎 |
中日本高速道路(株) |
| |
近田 博之 |
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) |
| |
石田 貴志 |
(株)道路計画 |
| |
野中 康弘 |
(株)道路計画 |
| 研究要旨 |
高速道路の片側2 車線区間である中央自動車道(下り線)多治見IC〜小牧東IC間の登坂車線設置区間において,我が国で初めて付加追越車線の試行運用を実施した。登坂車線運用時と付加追越車線運用時の交通状況を比較分析した結果,付加追越車線運用によってキープレフトが促進され,特に低速の貨物車の最外側車線利用が顕著になった。また,相対的に速度が低い車両がより外側車線を利用するようになり,車線間の速度階層が明確になった。さらに,相対的に速度が高い最内側車線において車群形成が抑制されたことで追越行動の自由度が高まり,同時に危険を誘発する恐れのある左側からの追越行動が減少したことなど,付加追越車線運用が望ましい交通状況の実現に寄与できることを確認した。 |
|
| |
<安全の泉賞> |
| |
論文番号52.「単路部における無信号二段階横断方式の評価」(研究論文)
| ○ |
石山 良太 |
名古屋大学 |
 |
| |
後藤 梓 |
元:名古屋大学 (現:国土技術政策総合研究所) |
| |
中村 英樹 |
名古屋大学 |
| 研究要旨 |
わが国の無信号横断歩道では,横断者の安全・円滑な横断が確保されているとは言い難い現状にある。これに対して横断者の優先権を確保するため,近年,「二段階横断方式」すなわち道路中央部に設けられた交通島を利用して横断歩道を二段階で渡る方式が注目されている。しかし,わが国における適用事例はまだ限られており,効果を定量的に示すことが望まれる.本研究では,ビデオ観測データに基づき,横断者の横断判断に対して,横断所要時間および接近する車両の位置と速度が与える影響を分析した。そのうえで,二段階横断方式適用時のクリティカルギャップの変化を,横断者の車両交通流に対するギャップ選択モデルにより推定した。また,このクリティカルギャップを用いて横断者の平均遅れを計算することにより,円滑性の向上効果を定量的に評価した。 |
|
| |
|